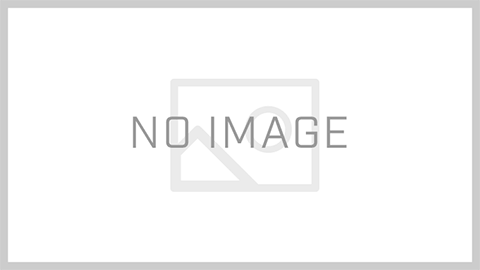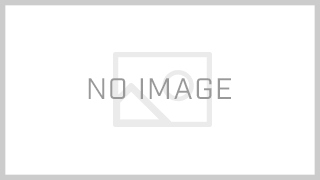表面張力-2|界面=境界
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
表面張力の話をする前に、界面について触れておかなければいけません。
界面とはモノとモノの境界のことをいいます。
前回の写真であれば空気と水の境界が界面であり、たとえば机に手を置いていれば机と手の間の境界が界面です。
そんな風に考えると、そこら中に界面はあります。
たくさんある界面は、界面を作っている物質の状態で分類できます。
物質の状態には気体、液体、固体の3種類があるので、これで界面の種類を整理するわけです。
この分類でいくと何種類の界面に分けられるでしょうか?
気体と気体の組み合わせでは界面ができないので、それ以外の組み合わせで考えてください。
そうすると全部で5種類に分けられます。
気体/液体界面、気体/固体界面、液体/液体界面、液体/固体界面、固体/固体界面の5種類です。
液体と液体の組み合わせは違和感があるかもしれませんが、水と油のような組み合わせだと考えてください。
そしてこのような界面の性質を表すものが界面張力(表面張力)です。
ところで界面と表面は何か違うのかということですが、基本は同じでどちらも境界を表わしています。
相手が気体の場合は特別に表面と呼んでいます。
一般に表面という言葉のほうがなじみがあるので、タイトルには表面張力という言葉を使っています。
コップの水の実験も表面ですし。
たまに両者をごちゃごちゃに使ってしまうかもしれませんが、その点はあまり気にしないでください。
次回は界面張力を説明します。