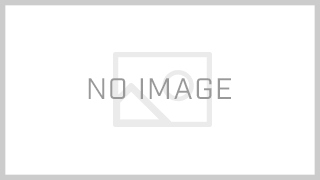濃度-12|電解質溶液のモル分率

以前、モル分率を紹介したとき、塩化ナトリウム水溶液を例として計算しました。

いわゆる食塩水なのでイメージしやすいかな、と考えたからです。
そのときに、「モル分率の計算で塩化ナトリウムの電離を考慮する必要はありませんか?」とご指摘がありました。
ご指摘のとおりで、すっかり頭から抜けていました。
あらためて考えてみると、この問題はなかなかややこしいです。
今回は、電解質水溶液のモル分率について学んだことを紹介します。
電離を考慮しない場合
以前に計算した \(\small 1\,\text{mol}\,\text{kg}^{-1}\) 塩化ナトリウム水溶液のモル分率を考えましょう。
電離を考慮せず、塩化ナトリウムとして計算したモル分率は先に示しています。
結果は以下のとおりです。
\(\small\color{blue}{x_{\text{NaCl}}=0.0175\cdots(1)}\)
\(\small\color{blue}{x_{\text{water}}=0.982\cdots(2)}\)
電離を考慮した場合
水に溶解させると、塩化ナトリウムはナトリウムイオンと塩化物イオンに電離します。
\(\small\color{blue}{\text{NaCl}\rightarrow\text{Na}^{+}+\text{Cl}^{-}\cdots(3)}\)
すると、\(\small 1\,\text{mol}\) の塩化ナトリウムから \(\small 1\,\text{mol}\) のナトリウムイオンと \(\small 1\,\text{mol}\) の塩化物イオンができます。
したがって、この水溶液中には \(\small 1\,\text{mol}\) のナトリウムイオン、\(\small 1\,\text{mol}\) の塩化物イオン、そして \(\small 56\,\text{mol}\) の水が存在しています。
このことから、電離を考慮したモル分率は以下のように計算できます。
\(\small\color{blue}{x_{\text{Na}^{+}}=x_{\text{Cl}^{-}}=\displaystyle\frac{1\,\text{mol}}{1\,\text{mol}+1\,\text{mol}+56\,\text{mol}}=0.0172\cdots(4)}\)
\(\small\color{blue}{x_{\text{water}}=\displaystyle\frac{56\,\text{mol}}{1\,\text{mol}+1\,\text{mol}+56\,\text{mol}}=0.966\cdots(5)}\)
このように考えると、電解質の場合は電離を考慮するかどうかでモル分率が変わります。
では、\(\small 1\,\text{mol}\,\text{kg}^{-1}\) 塩化マグネシウム水溶液のモル分率はどうなるでしょうか。
水に溶解させると、塩化マグネシウムはマグネシウムイオンと塩化物イオンに電離します。
\(\small\color{blue}{\text{MgCl}_{2}\rightarrow\text{Mg}^{2+}+2\text{Cl}^{-}\cdots(6)}\)
すると、\(\small 1\,\text{mol}\) の塩化マグネシウムから \(\small 1\,\text{mol}\) のマグネシウムイオンと \(\small 2\,\text{mol}\) の塩化物イオンができます。
したがって、この水溶液中には \(\small 1\,\text{mol}\) のマグネシウムイオン、\(\small 2\,\text{mol}\) の塩化物イオン、そして \(\small 56\,\text{mol}\) の水が存在しています。
このことから、電離を考慮したモル分率は以下のように計算できます。
\(\small\color{blue}{x_{\text{Mg}^{2+}}=\displaystyle\frac{1\,\text{mol}}{1\,\text{mol}+2\,\text{mol}+56\,\text{mol}}=0.0169\cdots(7)}\)
\(\small\color{blue}{x_{\text{Cl}^{-}}=\displaystyle\frac{2\,\text{mol}}{1\,\text{mol}+2\,\text{mol}+56\,\text{mol}}=0.0339\cdots(8)}\)
\(\small\color{blue}{x_{\text{water}}=\displaystyle\frac{56\,\text{mol}}{1\,\text{mol}+2\,\text{mol}+56\,\text{mol}}=0.949\cdots(9)}\)
電解質の電離を考慮したときのモル分率は以上のように計算できます。
より厳密に考えてみる
水溶液中で電解質が電離していることを考えると、電離を考慮した計算方法が正しいと考えられます。
しかし上述の計算は、電解質が完全に電離した場合を想定しています。
塩化ナトリウムのような塩は水中で完全に電離していると考えて差し支えありません。
一方、酢酸のように水中で一部だけが電離するものであれば、厳密にはそれを考慮しなければいけません。
この計算は以下のように行うことができます。
溶媒を \(\small n_1\,[\text{mol}]\)、電離する前の電解質を \(\small n_2\,[\text{mol}]\)、電解質の電離度を \(\small\alpha\) とします。
電離度を考慮すると、溶液中でこの電解質が電離したときの陽イオンの物質量は \(\small\alpha\nu^{+}n_2\,[\text{mol}]\)、陰イオンの物質量は \(\small\alpha\nu^{-}n_2\,[\text{mol}]\) と表せます。
ここで、\(\small\nu^{+}\) と \(\small\nu^{-}\) は電離して生じるイオンの数を表します。
たとえば以下のようなものです。
\(\small\color{blue}{\text{NaCl}\rightarrow\text{Na}^{+}+\text{Cl}^{-}\qquad\nu^{+}=1、\nu^{-}=1}\)
\(\small\color{blue}{\text{MgCl}_2\rightarrow\text{Mg}^{2+}+2\text{Cl}^{-}\qquad\nu^{+}=1、\nu^{-}=2}\)
\(\small\color{blue}{\text{CuSO}_4\rightarrow\text{Cu}^{2+}+\text{SO}_{4}^{2-}\qquad\nu^{+}=1、\nu^{-}=1}\)
また、電離していない電解質の物質量は \(\small n_2-\alpha n_2=n_2(1-\alpha)\,[\text{mol}]\) です。
以上から、溶液中に存在している溶媒、電離していない電解質、電離した陽イオン、陰イオン、すべての物質量の和は次のとおり計算できます。
\(\small\color{blue}{\begin{align}n_{\text{total}}&=n_{1}+n_{2}(1-\alpha)+\alpha\nu^{+}n_{2}+\alpha\nu^{-}n_{2}\\&=n_{1}+n_{2}+(\nu^{+}+\nu^{-}-1)\alpha n_{2}\cdots(10)\end{align}}\)
上式を使うと、溶媒、電離していない電解質、電離した陽イオン、陰イオンのモル分率を表すことができます。
\(\small\color{blue}{x_{1}=\displaystyle\frac{n_{1}}{n_\text{total}}\cdots(11)}\)
\(\small\color{blue}{x_{2}=\displaystyle\frac{n_{2}(1-\alpha)}{n_\text{total}}\cdots(12)}\)
\(\small\color{blue}{x_{+}=\displaystyle\frac{\alpha\nu^{+}n_{2}}{n_\text{total}}\cdots(13)}\)
\(\small\color{blue}{x_{-}=\displaystyle\frac{\alpha\nu^{-}n_{2}}{n_\text{total}}\cdots(14)}\)
\(\small(10)\)~\(\small(14)\)式が電離を考慮した一般式と言えます。
いろいろなパターンに応用できます
電離しない非電解質を扱うのであれば、\(\small(10)\)~\(\small(14)\)式に \(\small\alpha=0\) を代入します。
\(\small\color{blue}{n_{\text{total}}=n_{1}+n_{2}\cdots(15)}\)
\(\small\color{blue}{x_{1}=\displaystyle\frac{n_{1}}{n_{1}+n_{2}}\cdots(16)}\)
\(\small\color{blue}{x_{2}=\displaystyle\frac{n_{2}}{n_{1}+n_{2}}\cdots(17)}\)
\(\small\color{blue}{x_{+}=x_{-}=0\cdots(18)}\)
いわゆる通常のモル分率の式が導かれます。
完全に電離する電解質を扱うのであれば、\(\small(10)\)~\(\small(14)\)式に \(\small\alpha=1\) を代入します。
\(\small\color{blue}{n_{\text{total}}=n_{1}+(\nu^{+}+\nu^{-})n_{2}\cdots(19)}\)
\(\small\color{blue}{x_{1}=\displaystyle\frac{n_{1}}{n_{1}+(\nu^{+}+\nu^{-})n_{2}}\cdots(20)}\)
\(\small\color{blue}{x_{2}=0\cdots(21)}\)
\(\small\color{blue}{x_{+}=\displaystyle\frac{\nu^{+}n_{2}}{n_{1}+(\nu^{+}+\nu^{-})n_{2}}\cdots(22)}\)
\(\small\color{blue}{x_{-}=\displaystyle\frac{\nu^{-}n_{2}}{n_{1}+(\nu^{+}+\nu^{-})n_{2}}\cdots(23)}\)
上述した、電離を考慮した場合の塩化ナトリウム水溶液や塩化マグネシウム水溶液のモル分率はこれらの式から計算できます。
モル分率だからややこしい?
\(\small(10)\)~\(\small(14)\)式を使えば、どのような場合でも計算できることがわかります。
しかし、毎回これらの式を使って厳密にモル分率を計算するのはあまり現実的ではないように思います。
たとえば、弱電解質の電離度は非常に小さい数値が多いので、そのモル分率は非電解質として扱ったときとそれほど差はありません。
また、問題を複雑にしているのはモル分率だから、とも言えます。
電離を考慮するかどうかの問題は、容量モル濃度や質量モル濃度など、その他の濃度でも同じです。
ただし、他の濃度とモル分率には大きな違いがあります。
それはモル分率が、含まれている成分の相対的な比率になっている点です。
ある成分の割合が変われば、他の成分の割合も影響を受けます。
そこが問題をより複雑にしているのでしょう。
他の濃度であれば、係数を導入することで比較的簡単に電離の影響を含めることができます。
そのあたりはまた別の機会に触れます。
電解質の電離は頭に入れておきましょう
今回の記事を書くにあたり、自分の理解不足もあったので、あらためていろいろと調べました。
そうすると、モル分率を含めてさまざまな濃度は電離を考慮しない形で示されていることが多かったです。
教科書の例題しかり、演習問題しかり(そもそも電解質ではなく非電解質のみの問題になっていることも多かったです)。
売られている電解質水溶液も電離を考慮していない濃度で表示されています。
たとえば、\(\small 1\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}\) 塩化ナトリウム水溶液は水溶液 \(\small 1\,\text{L}\) に \(\small 1\,\text{mol}\) の塩化ナトリウムが含まれています。
それもそのはずで、電離を考慮した濃度で表示すると複雑になることは容易に想像できます。
元が何 \(\small\text{mol}\) 入っているかわかれば、電離を考慮した濃度は自分で計算できるので、それほど問題にはなりません。
電解質であっても、まずは非電解質として濃度を計算しておくのが良さそうです。
とはいえ電離を考慮しなくてよいわけでもありません。
必要なときには、電離を考慮した場合の濃度を計算して使います。
凝固点降下や浸透圧など束一的性質と呼ばれるものは最たる例で、電離を考慮しないと間違って理解してしまいます。
たかが電解質、されど電解質。
しっかり理解して、意識した上で濃度を使い分けていきましょう。
(自戒を込めて…)