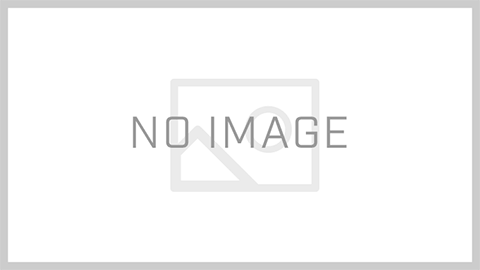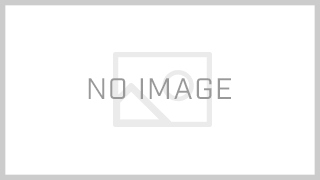平成27年度センター試験【化学】第1問 問1|原子の構成
原子は、正電荷をもつ原子核と負電荷をもつ電子から構成されます。
さらに原子核は、正電荷をもつ陽子と電荷をもたない中性子から構成されます。
原子核の大きさは原子の大きさのおよそ 10-4 ~ 10-5 程度で、仮に原子核を半径 1 cm の球とすると原子は半径 1 km 程度の球になることから、原子核は原子の中心に集中していることがわかります。
また、原子核を構成する陽子や中性子の質量は電子の質量のおよそ 1,840 倍になることから、原子の中心に集中している原子核はとても重く、その周りを軽い電子が飛び回っているイメージです。
原子は記号で図1のように表わされます。
参考資料 図1
これは炭素の例ですが、左上の数字は質量数、左下の数字は原子番号を表わします(原子番号は省略されることがあります)。
原子番号は陽子数と等しく、また、原子が中性であれば電荷は ±0 となるので、原子番号は電子数とも等しくなります。
原子番号=陽子数=電子数 (2つ目の等号は原子が中性のとき)
質量数は原子核を構成している陽子と中性子の数の和を表わします。
質量数=陽子数+中性子数
陽子数は原子番号と等しいので、次の関係が成り立ちます。
質量数=原子番号+中性子数
したがって左上の数字(質量数)と左下の数字(原子番号)の差をとると、中性子数が得られます。
質量数-原子番号=中性子数
原子番号が同じであれば元素記号は同じですが、中性子の数が違うと同じ元素でも質量数が違ってきます。
参考資料 図2
このような原子どうしを同位体といいます。
似たような言葉で同素体がありますが、こちらは酸素とオゾンやグラファイトとダイヤモンドのように、同じ元素の単体で性質や構造が異なる物質のことをいうので注意が必要です。
ちなみに問題で「水素以外の原子」と断っているのは、質量数 1 の水素原子の中性子数は 0 であり、選択肢に問題が生じるためです。